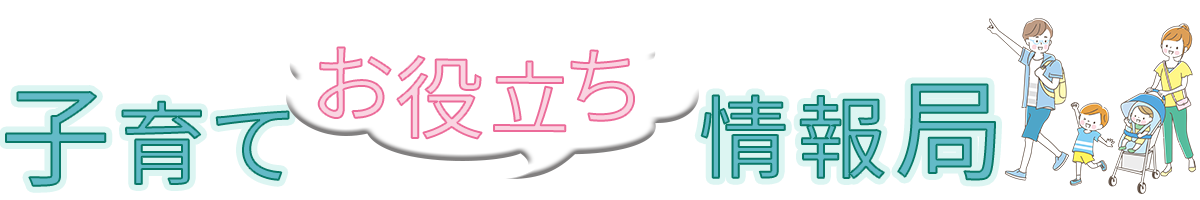1歳半のお子さんを育てるママの皆さん、毎日お疲れ様です!
お子さんのイヤイヤ期、どのように対応していますか?
「イヤイヤ」が止まらなくて、途方に暮れていませんか?
もしかすると、「どうしてうちの子だけこんなに激しいの?」と悩んでいる方もいるかもしれません。
でも大丈夫です!
それは決してあなたの子育てが間違っているわけではないんです。
 ぽんママ
ぽんママ実は私も、息子のイヤイヤ期には本当に苦労しました。
これから娘にもこの時期がやってくると思うと、気が重いです・・・。
朝から晩まで「イヤ!」の嵐で、心が折れそうになったことも一度や二度ではありません。
イヤイヤ期は子どもの成長にとって、とても大切なステップなんです。
この記事では、そんなイヤイヤ期に悩むママに向けて、イヤイヤ期の原因から具体的な対応策まで、詳しく解説していきますね。
1歳半のイヤイヤ期の特徴は?
この時期の子どもの心の変化
1歳半頃の子どもは、[marker color=”yellow”]自我の芽生え[/marker]の真っただ中にいます。
「自分でやりたい」「自分で決めたい」という気持ちが強くなる一方で、まだ言葉で上手に表現できないもどかしさを感じています。
これまで「かわいい赤ちゃん」だった我が子が、急に反抗的になったように感じるかもしれません。
でも、これは子どもが順調に成長している証拠なんです。
行動の背景にある心理
子どもが「イヤイヤ」を言う時、実は様々な感情が混在しています。
- 「自分でやりたい」という自立心
- 「思い通りにならない」という欲求不満
- 「分かってもらえない」という不安
- 「注目してもらいたい」という愛情欲求



うちの子も何でも「イヤ!」って言うけど、そんな気持ちがあったのね



そうなんです。一見わがままに見えても、子どもなりに一生懸命気持ちを伝えようとしているんですよ!
1歳半のイヤイヤ期がひどくなる原因
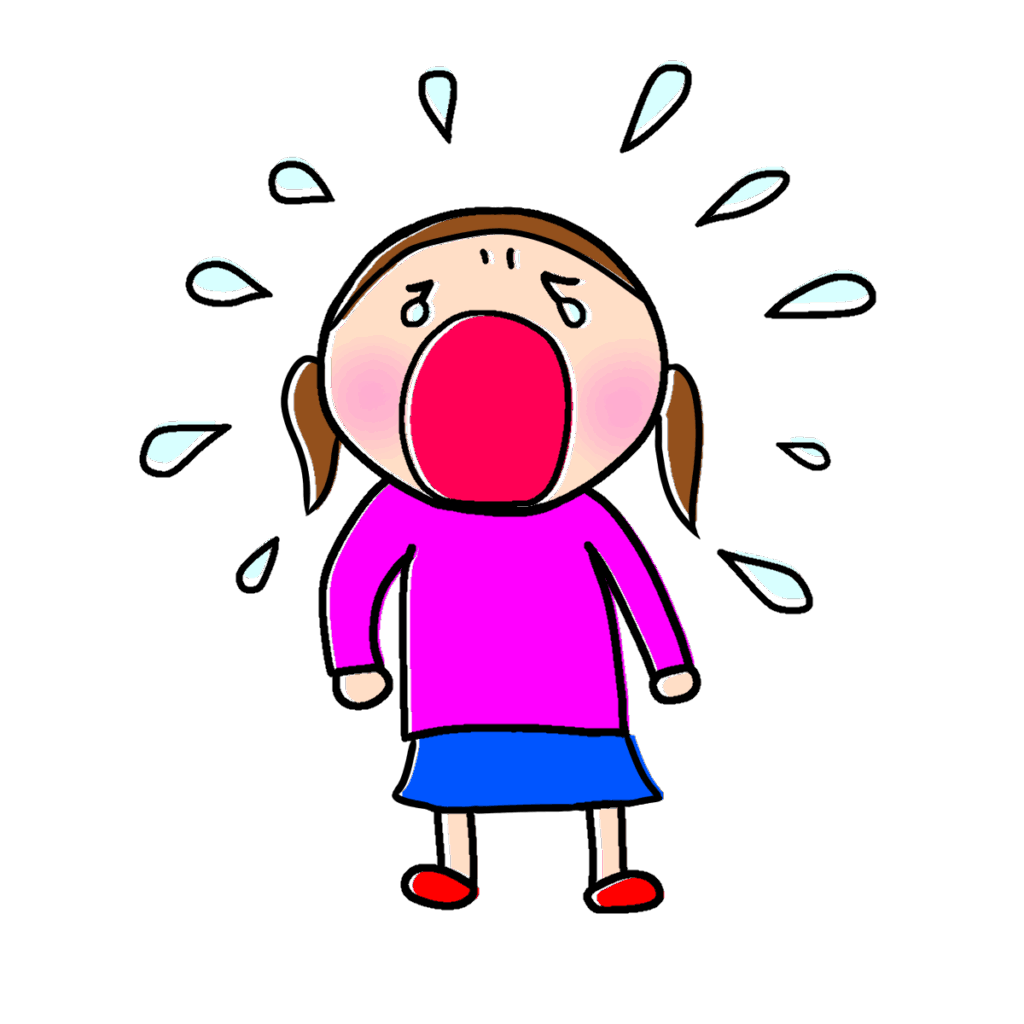
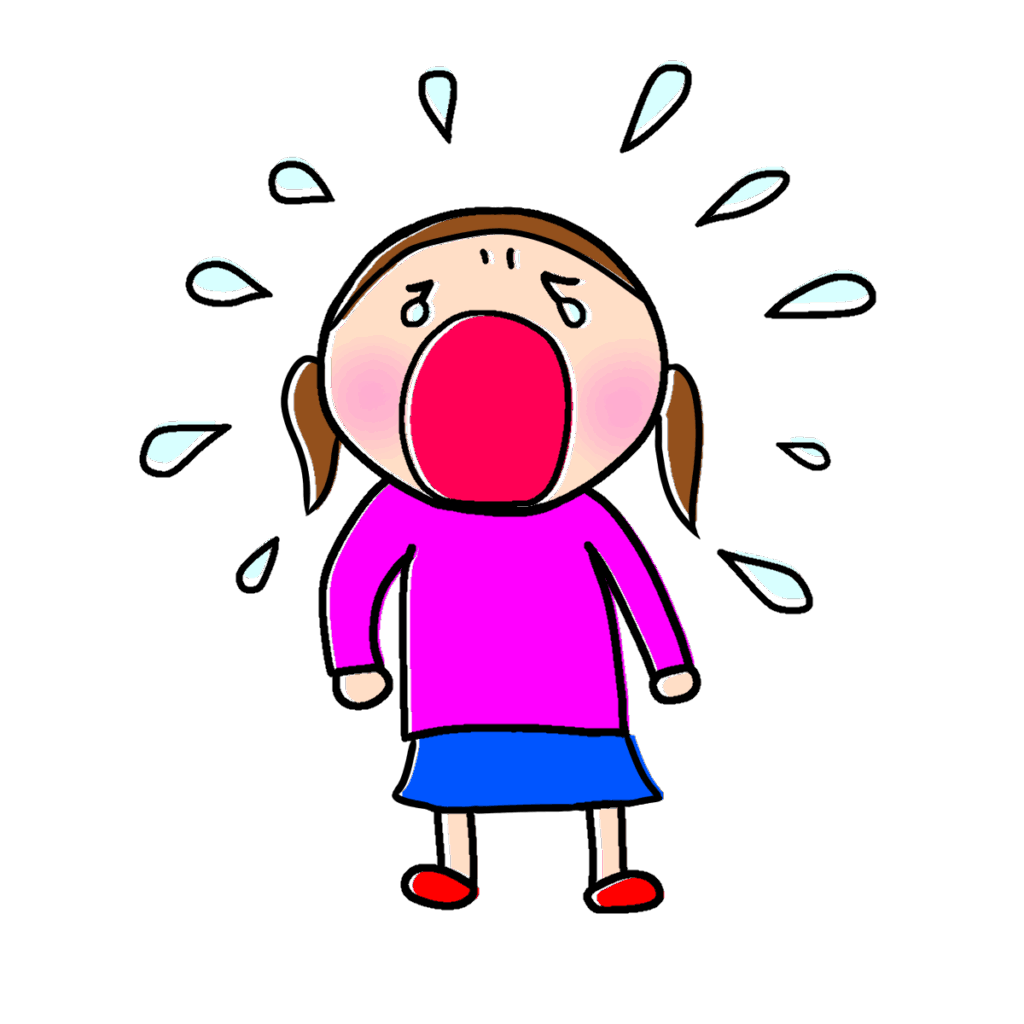
1. 言葉の発達と気持ちのギャップ
1歳半の子どもは、言いたいことがたくさんあるのに、まだ言葉で表現する力が追いついていません。
この[marker color=”yellow”]もどかしさ[/marker]が、「イヤイヤ」という形で表れることが多いんです。
私の子も、この時期は何か伝えたそうに「あー!」「うー!」と指差しながら叫んでいました。
分かってもらえないと、床に寝転んで大泣きすることもしばしば。
2. 自分でやりたい欲求の高まり
「自分でやりたい」という気持ちが強くなる一方で、まだ上手にできないことが多いのがこの時期。
靴を履こうとして上手くいかない、コップを持とうとしてこぼしてしまう…そんな時に「イヤイヤ」が爆発します。
3. 生活リズムの変化
1歳半頃は、昼寝の回数が減ったり、食事の内容が変わったりと、生活リズムが変化する時期でもあります。
これらの変化が、子どもの情緒を不安定にすることもあります。



生活の変化って、大人でもストレスを感じるものですよね。



確かに。子どもならなおさら大変なのかも
4. 環境の変化への敏感さ
1歳半の子どもは、環境の変化にとても敏感です。
お出かけ先、新しい人との出会い、いつもと違う時間帯の活動…こうした変化が「イヤイヤ」を引き起こすことがあります。
困った場面もこれで安心!
シーン別・上手な声かけ&対応術
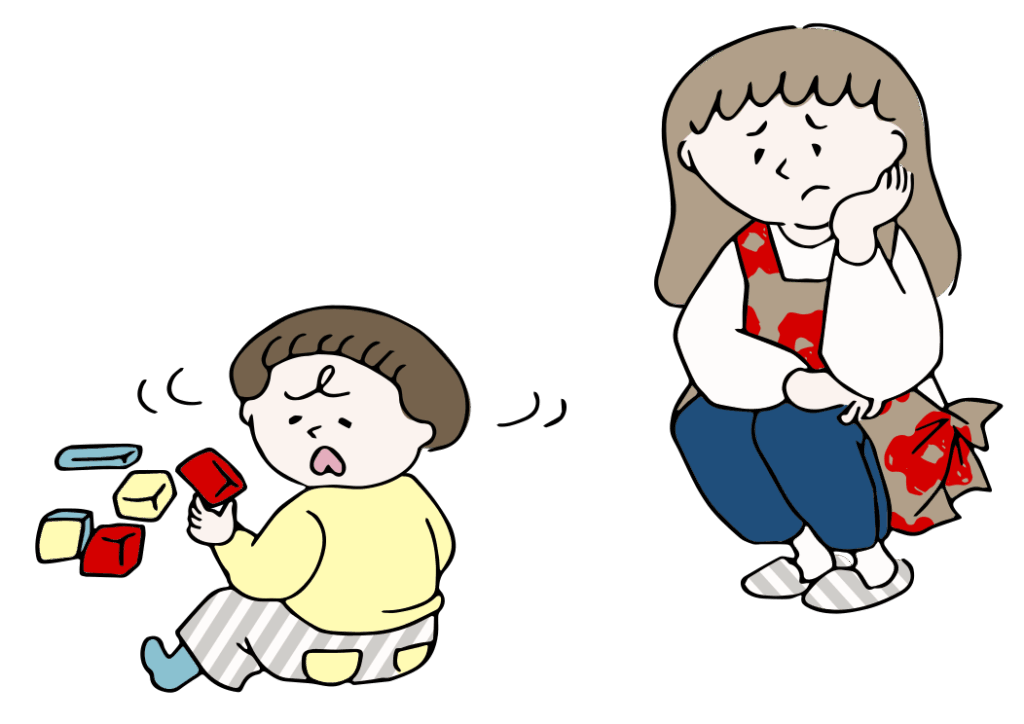
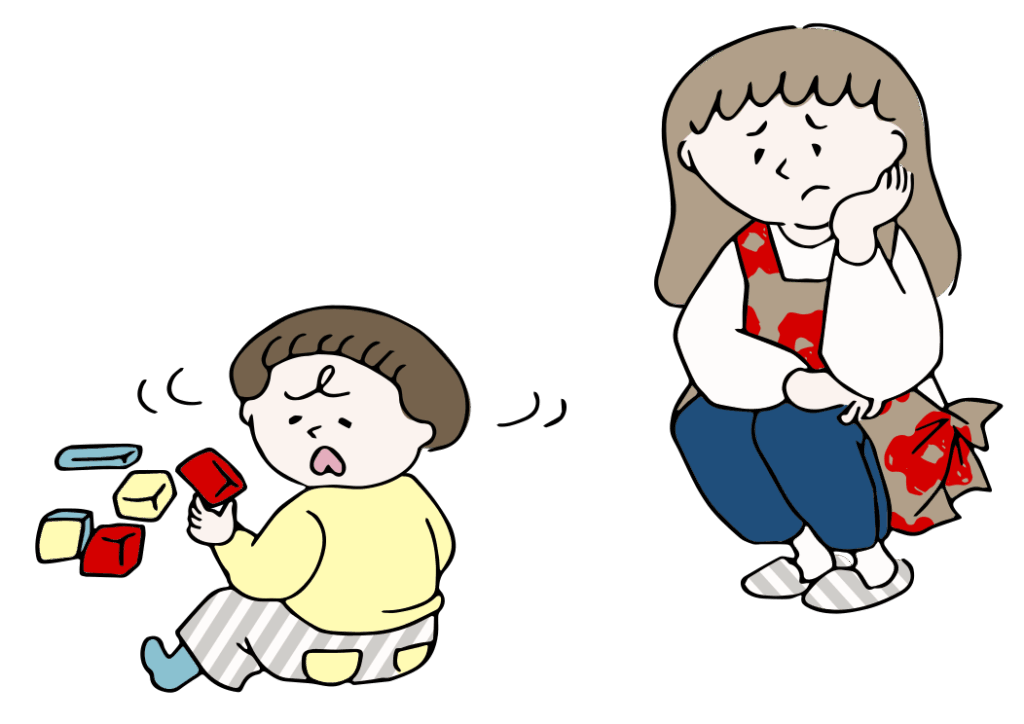
Case1. 着替えを嫌がる時は?
原因
- 着替えること自体への抵抗
- 自分で選びたい気持ち
- 今の遊びを中断されたくない
この場合の対応策
- ★選択肢を提示する
-
「赤いシャツと青いシャツ、どっちがいい?」 「お着替えしてからおやつにする?それとも遊んでから?」などと、子どもに[marker color=”yellow”]選択権[/marker]を与えることで、「自分で決めた」という満足感を得られます。
- ★楽しい雰囲気を作る
-
「お洋服さんとお話ししてみよう」「腕を通すよ〜、バンザイ!」 着替えを楽しい遊びに変えることで、抵抗感を軽減できます。



私は、着替えの時によく「お洋服さんが『こんにちは』って言ってるよ」と声をかけていました。
子どもも「こんにちは」って返事して、楽しそうに着替えてくれることが多かったです。


楽しい時間になるような工夫が必要なんですね!
Case2. 食事を拒否する時は?
原因
- 食べ物への好き嫌い
- 自分で食べたい気持ち
- 遊びたい気持ちが強い
この場合の対応策
- ★自分で食べる機会を作る
-
手づかみで食べられるものを用意したり、スプーンを持たせたりして、「自分でやりたい」気持ちを満たしてあげましょう。
- ★食事環境を見直す
-
テレビを消して集中できる環境を作ったり、好きなキャラクターの食器を使ったりして、食事への興味を引きましょう。
- ★無理強いしない
-
「食べなさい」と強要するより、「一口だけ食べてみる?」と優しく誘ってみましょう。



毎回イライラしちゃうけど、子どももプレッシャーに感じちゃっているかも。



そうですね。食事の時間って、親子の戦いになりがちですが、楽しい時間にしたいですよね。
Case3. お片付けを嫌がる時は?
原因
- 遊びを中断されたくない
- 片付けの方法が分からない
- 大人の都合で急かされている
この場合の対応策
- ★予告をする
-
「あと5分遊んだら、お片付けしようね」 急に片付けを始めるのではなく、[marker color=”yellow”]心の準備[/marker]をする時間を作ってあげましょう。
- ★一緒に片付ける
-
「ママと一緒にお片付けしよう」「この箱にブロックを入れてくれる?」 子どもと一緒に片付けることで、やり方を教えながら達成感も味わえます。
- ★片付けを遊びにする
-
「お片付け競争しよう」「おもちゃさんをお家に帰してあげよう」などと、 楽しい要素を加えることで、抵抗感を軽減できます。



ついつい、大人の都合を押し付けてしまっていたかも。
子どもだって、心の準備が必要ですよね。


はい、子どもってこちらが思う以上に、いろいろと考えながら、遊んでいたりします。
子どもが終わりを意識しやすいような声掛けをしたり、お片付けも楽しいと思えるように、気持ちをもっていってあげられると良さそうです!
Case4. 外出先でのイヤイヤ、どうする?
事前にできる準備
- 子どもの機嫌の良い時間帯を選ぶ
- お気に入りのおもちゃやおやつを持参
- 外出の目的を簡単に説明する
この場合の対応策
- ★場所を変える
-
人が多い場所では、静かな場所に移動してから対応しましょう。
- ★抱っこで落ち着かせる
-
興奮している時は、まず抱っこして安心させることが大切です。
- ★気をそらす
-
「あっちに車がいるよ」「お花がきれいだね」などと、 別のことに注意を向けることで、イヤイヤから抜け出せることがあります。



お出かけ中にぐずられると、本当に大変。。。
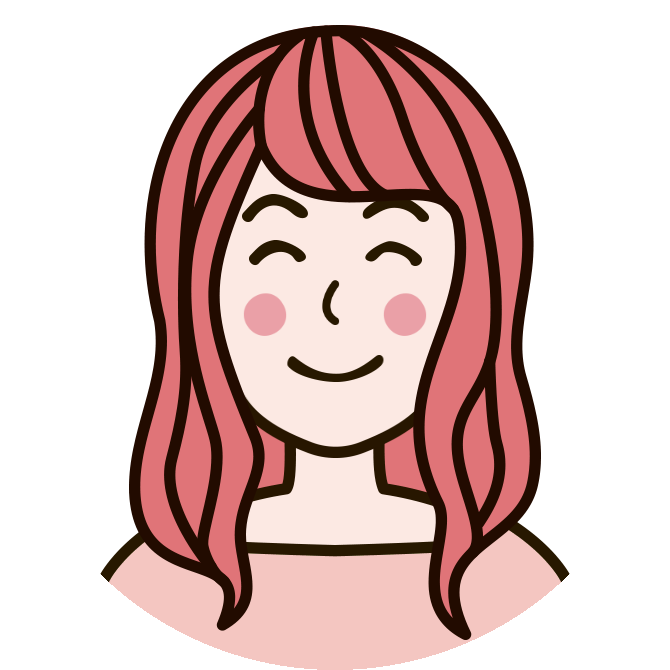
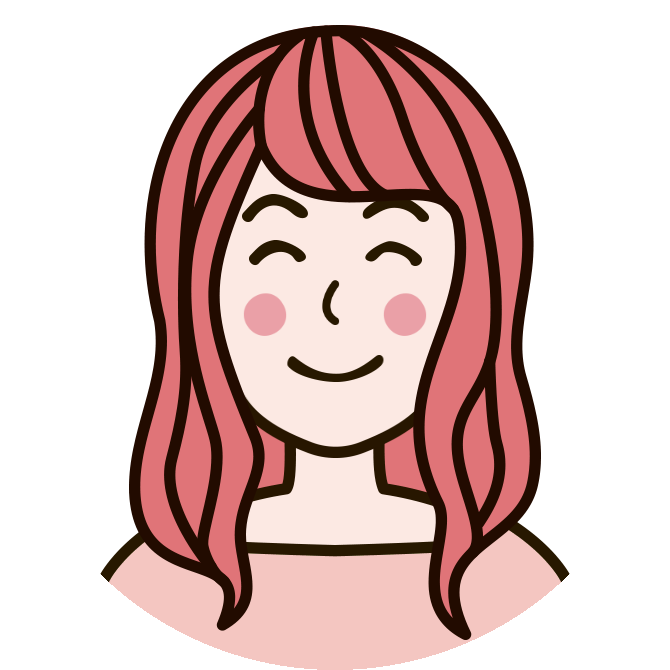
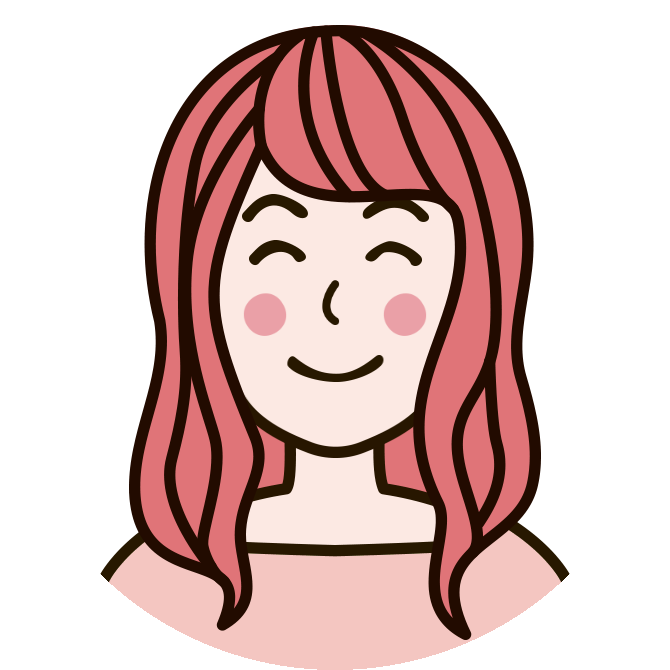
はい、周りの目も気になりますよね。
まずは場所を移動するなどして、落ち着いてから対応できると良いですね。
Case5. 夜のイヤイヤ、どうする?
原因
- 一日の疲れや刺激の蓄積
- 眠くて機嫌が悪い
- 親の疲れが子どもに伝わる
この場合の対応策
- ★早めの就寝準備
-
機嫌が悪くなる前に、お風呂や歯磨きを済ませておきましょう。
- ★静かな環境を作る
-
照明を暗くして、落ち着いた雰囲気を作ることで、子どもの気持ちも落ち着きます。
- ★スキンシップを増やす
-
抱っこしたり、背中をさすったりして、[marker color=”yellow”]安心感[/marker]を与えましょう。
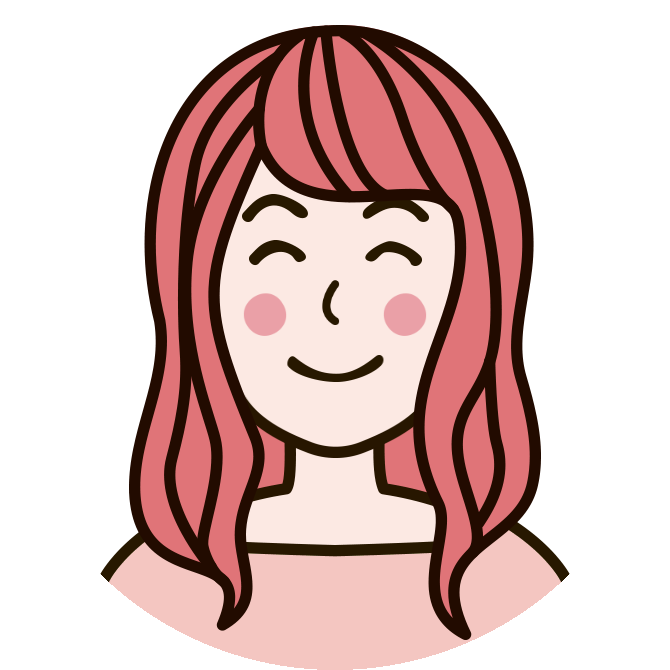
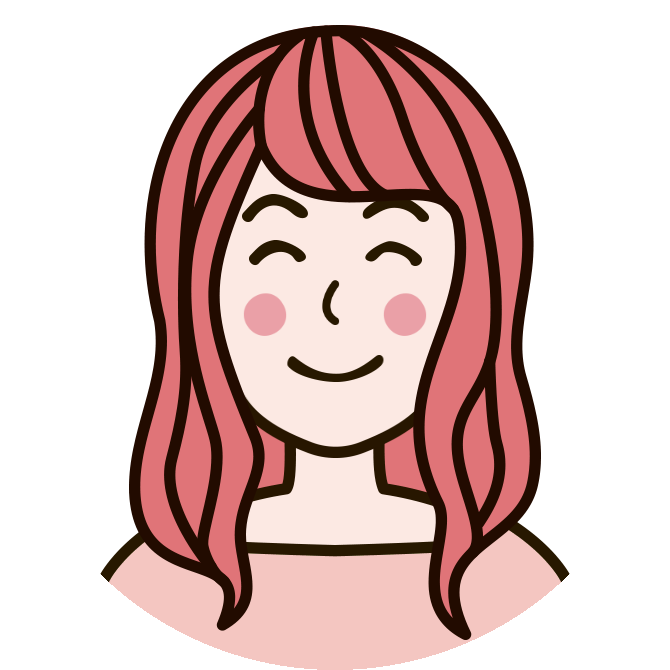
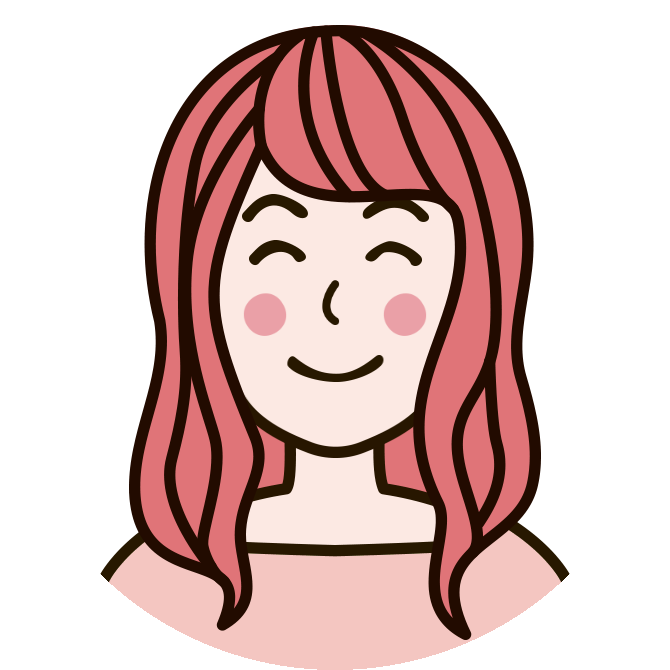
夜のイヤイヤって、一日の疲れもあって特に大変ですよね



本当に。でも子どもも疲れているんだと思うと、少し優しくなれるかも。
子どもの気持ちに寄り添う!
4ステップ対応術


気持ちを受け止める
(まずは共感)
子どもが「イヤイヤ」と言った時、まずは気持ちを受け止めることから始めましょう。
具体的な声かけ例
- 「イヤだったんだね」
- 「悲しかったね」
- 「怒っているんだね」
子どもの気持ちを[marker color=”yellow”]言葉にしてあげる[/marker]ことで、「分かってもらえた」という安心感を得られます。
選択肢を提示する
(自主性を尊重)
気持ちを受け止めた後は、子どもが自分で選べる選択肢を提示しましょう。
選択肢の例
- 「お水とお茶、どっちがいい?」
- 「手をつないで歩く?それとも抱っこ?」
- 「今やる?それとも後でやる?」
タイミングを見極める
(落ち着くまで待つ)
興奮している時は、何を言っても聞き入れてもらえません。
まずは子どもが落ち着くまで、そっと見守ることも大切です。
落ち着くまでの対応
- 安全な場所で見守る
- 必要以上に声をかけない
- 子どもが求めてきたら応じる



私も最初は「早く泣き止んでほしい」と思って、あれこれ声をかけていました。
でも、少し距離を置いて見守っていると、子どもが自分で気持ちを整理する力があることに気づきました。
気持ちを切り替える
(次の活動へ)
子どもが落ち着いたら、次の活動に気持ちを向けるサポートをしましょう。
切り替えのテクニック
- 「今度は○○しようか」
- 「お腹すいた?」
- 「外を見てみよう」
月齢に合わせた工夫を!
ポイントをご紹介
1歳6ヶ月〜1歳9ヶ月
この時期は、まだ言葉での表現が難しいので、[marker color=”yellow”]非言語コミュニケーション[/marker]が重要です。
対応のポイント
- 身振り手振りを使って説明する
- 表情豊かに接する
- スキンシップを多く取る
1歳9ヶ月〜2歳
言葉の理解が進んでくるので、簡単な説明も有効になります。
対応のポイント
- 短い言葉で理由を説明する
- 「後で」「あとちょっと」などの時間概念を使う
- 選択肢を2つに絞って提示する



月齢によって対応を変えるって、難しそうですが大切なことですね。



そうですね。子どもの成長に合わせて対応を変えていけると良さそうです!
がんばりすぎないで!
“親の心”も大切にするヒント
完璧を求めすぎない
イヤイヤ期の対応に「正解」はありません。
同じ方法でも、日によって効果が違うことはよくあります。
「今日はうまくいかなかった」という日があっても、それは普通のことです。
他の子と比較しない
「○○ちゃんは素直なのに、うちの子は…」 そんな風に比較してしまうことがあるかもしれません。
でも、子どもにはそれぞれの個性とペースがあります。
我が子の成長を、その子なりのペースで見守りましょう。
親の感情をコントロールする
イヤイヤ期の子どもの対応は、本当に忍耐力が必要です。
イライラしてしまうのは当然のことですが、その感情をそのままぶつけてしまうと、子どもも不安になってしまいます。
感情コントロールのコツ
- 深呼吸をする
- 一旦その場を離れる
- 「成長の証」と自分に言い聞かせる



私も、子どもが床に寝転んで大泣きしている時に、「もう知らない!」と言いたくなることがありました。
でも、「今はイヤイヤ期という大切な時期なんだ」と思うことで、少し冷静になれました。
周りのサポートを活用する
一人で抱え込まず、家族や友人、地域のサポートを活用しましょう。
活用できるサポート
- パートナーや家族との分担
- 子育てサークルでの情報交換
- 保健師さんへの相談
- 一時保育の利用



一人で頑張りすぎないことが、結果的に子どもにとっても良いんですね



そうですね。ママが笑顔でいることが、子どもにとって一番かもしれません。
みんなが気になるQ&A
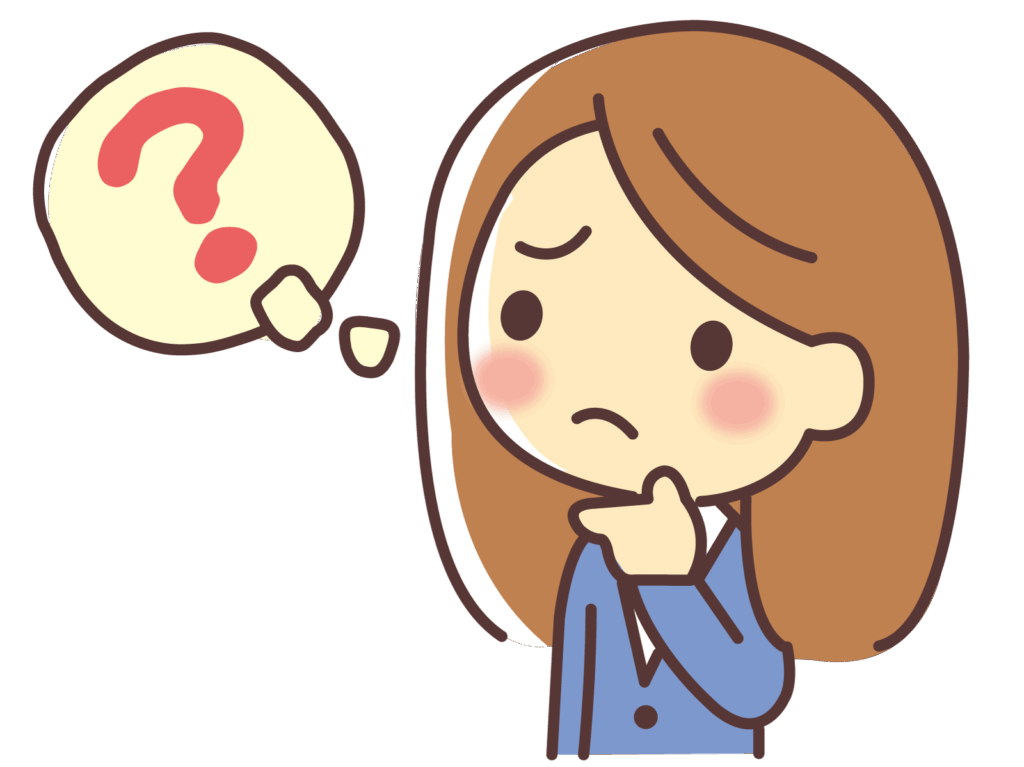
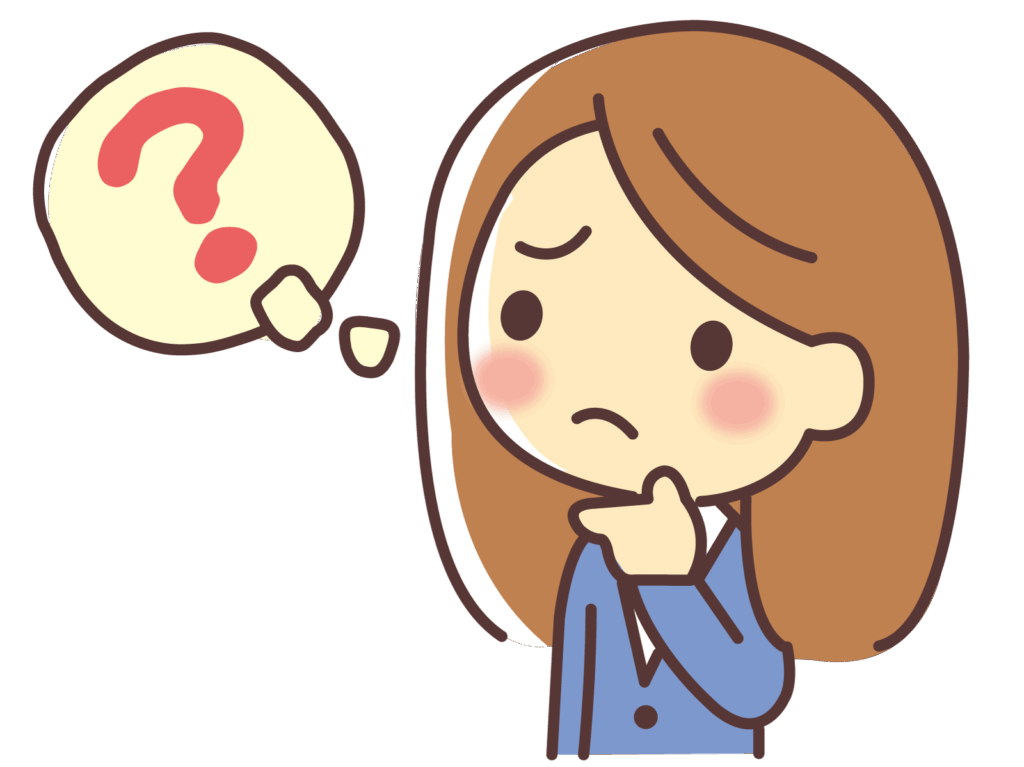
これって相談のタイミングかも?
迷ったときの目安
以下のような場合は、小児科医や保健師、児童心理士などの専門家に相談することをおすすめします。
- イヤイヤの程度が極端に激しい
- 自分や他人を傷つけるような行動がある
- 発達の遅れが心配
- 親自身の精神的な負担が大きい
- 家族関係に深刻な影響が出ている
一人で悩まず、専門家のアドバイスを受けることで、新しい視点が得られることがあります。
まとめ
1歳半のイヤイヤ期は、子どもの[marker color=”yellow”]成長の証[/marker]です。
「自分でやりたい」「自分で決めたい」という気持ちが芽生える大切な時期だからこそ、親としては戸惑うことも多いでしょう。
でも、子どもの気持ちを理解し、適切な対応をすることで、この時期を乗り越えることができます。
そして、イヤイヤ期を通して、子どもは自分の感情をコントロールする力や、人との関わり方を学んでいくのです。
大切なのは、子どもの気持ちを尊重しながら、親自身も無理をしないこと。
完璧を求めすぎず、「今日も一日お疲れさま」という気持ちで、子どもと一緒に成長していきましょう。



大変な時期だからこそ、子どもの気持ちを理解する姿勢が、将来の信頼関係につながるんです



そう思うと、イヤイヤ期も貴重な時間なのかもしれませんね!
この記事が、イヤイヤ期で悩んでいるママたちの少しでもお役に立てれば嬉しいです。
一人で抱え込まず、子どもと一緒に、この大切な成長の時期を乗り越えていきましょうね。