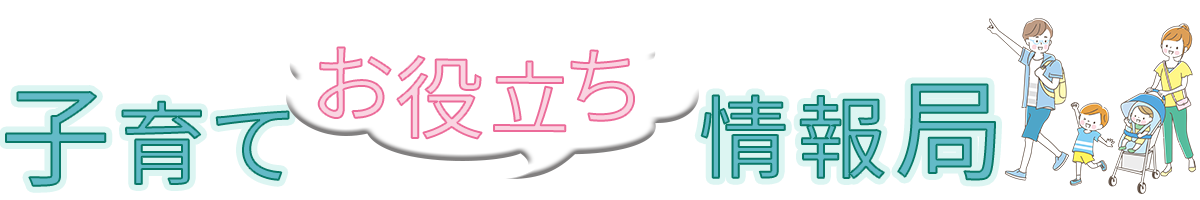こんにちは!
生後6ヶ月の赤ちゃんを育てているママの皆さん、お昼寝について悩んでいませんか?
- うちの子、全然お昼寝してくれない…
- やっと寝たと思ったら、30分で起きちゃう
- お昼寝しないから夜も機嫌が悪くて…
そんな声を本当によく聞きます。
実は私も同じような経験をしました。
生後6ヶ月頃って、赤ちゃんの[marker color=”yellow”]睡眠リズムが大きく変わる時期[/marker]なんです。
 ぽんママ
ぽんママ私も毎日「今日はお昼寝してくれるかな?」ってドキドキしながら寝かしつけしていました。
うまくいかない日は本当に落ち込んだりして…
今日は、そんな悩みを抱えるママたちに向けて、[marker color=”yellow”]生後6ヶ月の赤ちゃんのお昼寝事情と困ったときの対策[/marker]について、私の体験も交えながらお話しします。
生後6ヶ月の赤ちゃんのお昼寝事情


この時期の睡眠の特徴
生後6ヶ月の赤ちゃんは、[marker color=”yellow”]睡眠リズムが大人に近づいてくる時期[/marker]です。
新生児の頃は1日の大半を眠って過ごしていた赤ちゃんも、この頃になると[marker color=”yellow”]起きている時間が長くなり[/marker]、[marker color=”yellow”]昼と夜の区別がついてきます[/marker]。
一般的に、[marker color=”yellow”]生後6ヶ月の赤ちゃんの睡眠時間は1日13~15時間程度[/marker]。
そのうち、[marker color=”yellow”]お昼寝は2~3回で、合計3~4時間くらい[/marker]が目安とされています。



うちの子は全然この通りじゃないけど、大丈夫なのかな?



はい!これはあくまでも目安で、赤ちゃんにはそれぞれ個性があるので、この通りでなくても心配しすぎる必要はないそうですよ!
お昼寝パターンの変化
生後6ヶ月頃になると、多くの赤ちゃんが3回のお昼寝から、2回のお昼寝へと移行し始めます。
午前中に1回、午後に1回というかんじになる子も多いです。
でも、この移行期間中は、睡眠リズムが不安定になりがちで、お昼寝をしない日があったり、お昼寝時間が短くなったりすることがよくあります。
私の子も、この時期は本当にお昼寝が安定しませんでした。
「昨日は2時間寝たのに、今日は30分で起きちゃった・・・」
なんてことは日常茶飯事。
最初は、「私の寝かしつけが下手なのかな」と自分を責めていましたが、これは成長の証なんだと知って、少し気持ちが楽になりました!



毎日バラバラで、もう何がなんだかわからない…



そうですよね。「なんで昨日は寝てくれたのに、今日は寝てくれないの?」って思うことありませんか?でも、これって赤ちゃんが順調に成長している証拠なんですよね。



そうなの?成長の証だったら、少し安心!
生後6ヶ月の赤ちゃんがお昼寝しない主な理由は?
1. 睡眠サイクルの変化
新生児の頃は深い眠りと浅い眠りの区別があまりなかったのですが、この時期になると睡眠サイクルがはっきりしてきて、浅い眠りの時に目が覚めやすくなります。
大人でも、眠りが浅い時にちょっとした音で目が覚めることがありますよね。
赤ちゃんも同じで、睡眠サイクルが変わることで、以前より起きやすくなってしまうんです。
2. 発達による影響
生後6ヶ月頃は、寝返りが上手にできるようになってきたり、お座りができる子も出てきたりと、身体的な発達が著しい時期です。
新しいことができるようになると、赤ちゃんは興奮状態になりやすく、なかなか眠りにつけなくなることがあります。
また、この時期は脳の発達も盛んで、たくさんの刺激や体験を処理するのに忙しいんです。
そのため、眠りが浅くなったり、短時間で目が覚めてしまったりすることがよくあります。
私の子も、寝返りを覚えた時期は、寝かしつけた後にコロコロ転がって遊んでいることもありました。
「今は眠るより動きたい時期なのね」って思うようにしていました。



せっかく寝たのに、寝返りで起きちゃった…どうしたらいいの?



これは本当によくあることなんです。
[marker color=”yellow”]新しい動きを覚えた赤ちゃんは、それを練習したくて仕方ない[/marker]んですよね。
少し時間をかけて見守ってあげることで、だんだん落ち着いてくるはずです。
3. 環境に敏感になる
生後6ヶ月の赤ちゃんは、周囲の環境に敏感になってきます。
光の明るさ、音、温度、湿度などの変化に反応しやすくなり、これらがお昼寝の妨げになることも。
特に、家族の生活音や外からの音に反応して起きてしまうことが多くなります。
私の家でも、宅配便のチャイムの音で起きちゃうことがよくありました。。。



宅配便のお兄さんには、どうしても取りに行けないときに「すみません、赤ちゃんが寝ているので…」って謝ったり、置き配をお願いすることもありました。みなさん理解してくれて助かりました。



せっかく寝たのに、電話で起きちゃった…なんでこのタイミングなの?



本当にそう思いますよね。
赤ちゃんが寝た瞬間に限って、なぜか電話が鳴ったり来客があったり…。
でも、これも[marker color=”yellow”]一時的なもの[/marker]。
赤ちゃんもだんだん音に慣れてきて、そのうち起きにくくなってきますよ。
4. 離乳食の影響
生後6ヶ月頃から離乳食が始まると、消化のリズムも変わってきます。
お腹が空いて眠れなかったり、逆に満腹すぎて眠れなかったりすることが出てくるそう。
また、新しい食材に対する体の反応で、赤ちゃんが体調の変化を敏感にかんじとって眠れないということもあります。
こんなとき、どうする?お昼寝の問題パターン別の対策


短時間で起きてしまうパターン
30分~1時間で起きてしまう原因
- 睡眠サイクルの変化
- 環境の変化(音、光、温度)
- 寝る前の興奮状態
- 不快感(おむつ、空腹など)
この場合の対策
- 環境を整える
お部屋を暗くして、適度な温度(20~22度)に保ちましょう。
カーテンを閉めて、できるだけ静かな環境を作ることが大切です。
私は、お昼寝の時間には家族にも協力してもらって、テレビの音量を下げたり、電話に出る時は別の部屋に移動したりしていました。



赤ちゃんの睡眠って家族みんなの生活リズムに関わるんですよね。



家族みんなで、環境を整えていけるといいな!
赤ちゃんがしっかりとお昼寝できた日は、夜泣きが少なくなるなど、 [marker color=”yellow”]家族全員の生活の質[/marker]に関わってくることもありますよね。
みんなで協力して、乗り越えていきましょう。
- 入眠前のルーティンを作る
[marker color=”yellow”]毎回同じ流れで寝かしつけをすること[/marker]で、赤ちゃんに[marker color=”yellow”]「これから寝る時間だよ」というサイン[/marker]を送ることができます。
[marker color=”yellow”]絵本を読んだり、優しく歌を歌ったり、お気に入りのタオルを持たせたり[/marker]と、赤ちゃんがリラックスできる方法を見つけましょう。
起きてしまった時の対応は?
もし、短時間で起きてしまった時は、すぐに抱き上げずに、少し様子を見てみましょう。
時々、目が覚めても再び眠りにつくことがあります。
ただし、泣いている場合は、優しく声をかけたり、背中をトントンしたりして、安心させてあげましょう。
全くお昼寝しないパターン
お昼寝を拒否する原因
- 夜の睡眠時間が長すぎる
- お昼寝のタイミングが合わない
- 過度の刺激や興奮
- 体調不良
この場合の対策
- 生活リズムを見直す
[marker color=”yellow”]夜の睡眠時間が長すぎると、お昼寝をしなくなる[/marker]ことがあります。
起床時間を少し早めたり、お昼寝のタイミングを調整したりして、[marker color=”yellow”]1日の生活リズムを整えましょう。[/marker]
- 眠気のサインを見逃さない
赤ちゃんの[marker color=”yellow”]眠気のサイン[/marker]を見逃さないことが大切です。
[marker color=”yellow”]あくびをしたり、目をこすったり、機嫌が悪くなったり[/marker]したら、眠気のサインかもしれません。



あくびした!今がチャンスかも!



そうそう! その通りです!
[marker color=”yellow”]このタイミングを逃さずに[/marker]、寝かしつけを始めましょう。
眠気のサインを見つけた時の「今だ!」という気持ち、すごくよく分かります。
- 活動と休息のバランス
午前中は適度に活動させて、お昼寝前には[marker color=”yellow”]クールダウンの時間[/marker]を作りましょう。
[marker color=”yellow”]激しい遊びの直後だと、興奮して眠れない[/marker]ことがあります。
ステップごとに実践!お昼寝サポート方法
【第1ステップ】環境を整える(1週間)
まずは、[marker color=”yellow”]睡眠環境を整える[/marker]ことから始めましょう。
★チェックリスト
- 部屋の明るさ:カーテンを閉めて薄暗くする
- 温度:20~22度に保つ
- 湿度:50~60%を目安に
- 音環境:できるだけ静かに
- 寝具:清潔で快適な状態に



私の場合、最初は「昼間だから明るくても大丈夫」と思っていましたが、カーテンを閉めて薄暗くしたら、お昼寝の時間が少し長くなりました!
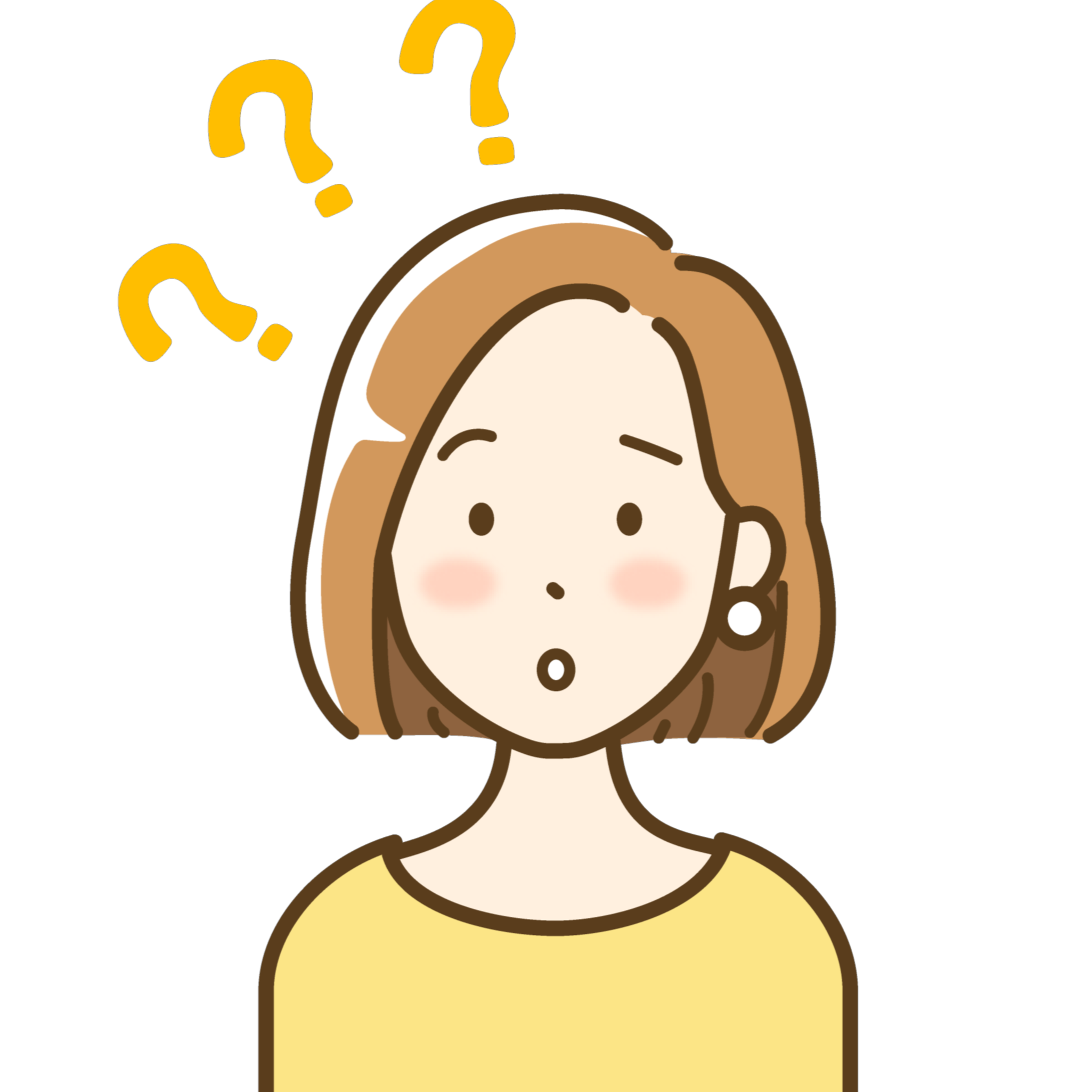
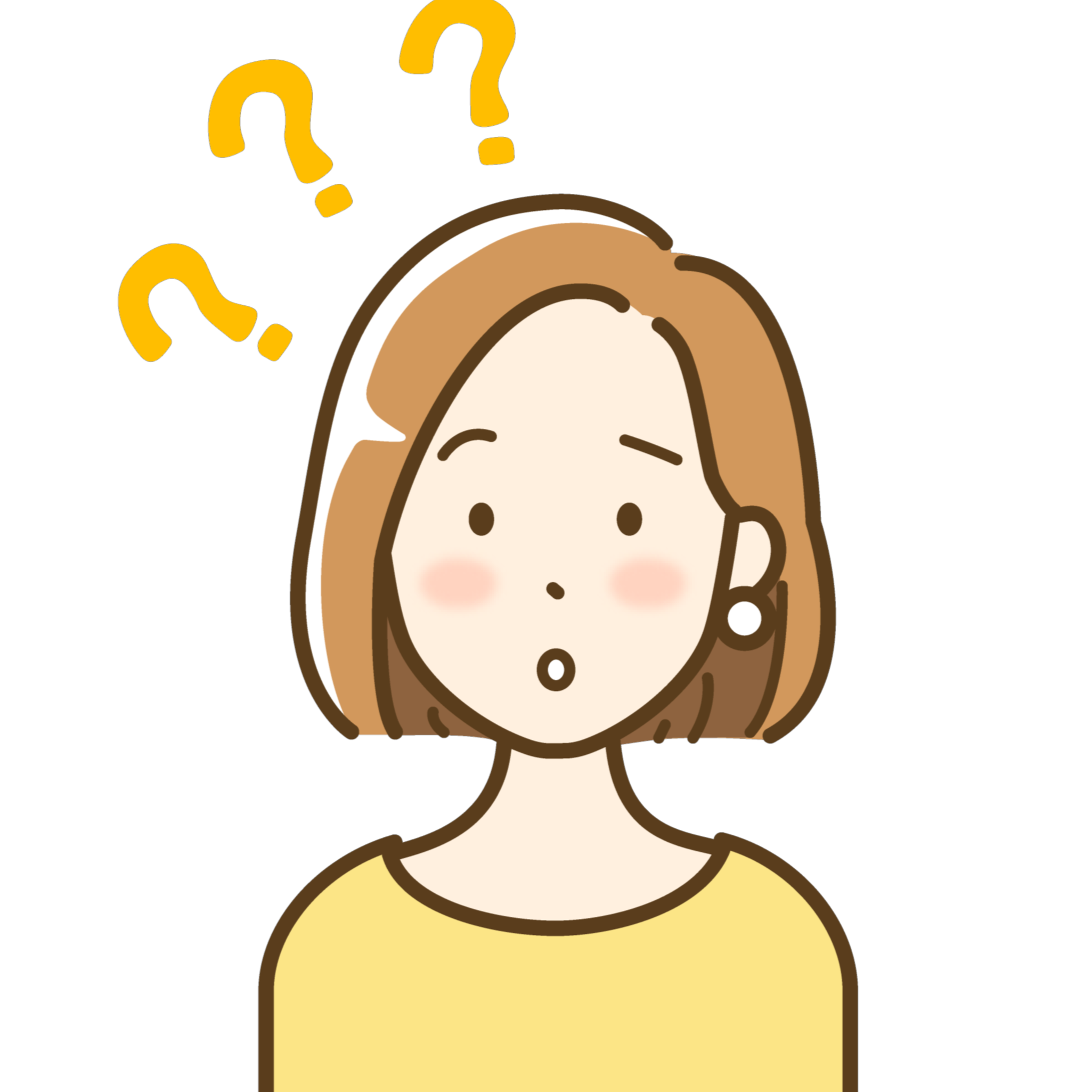
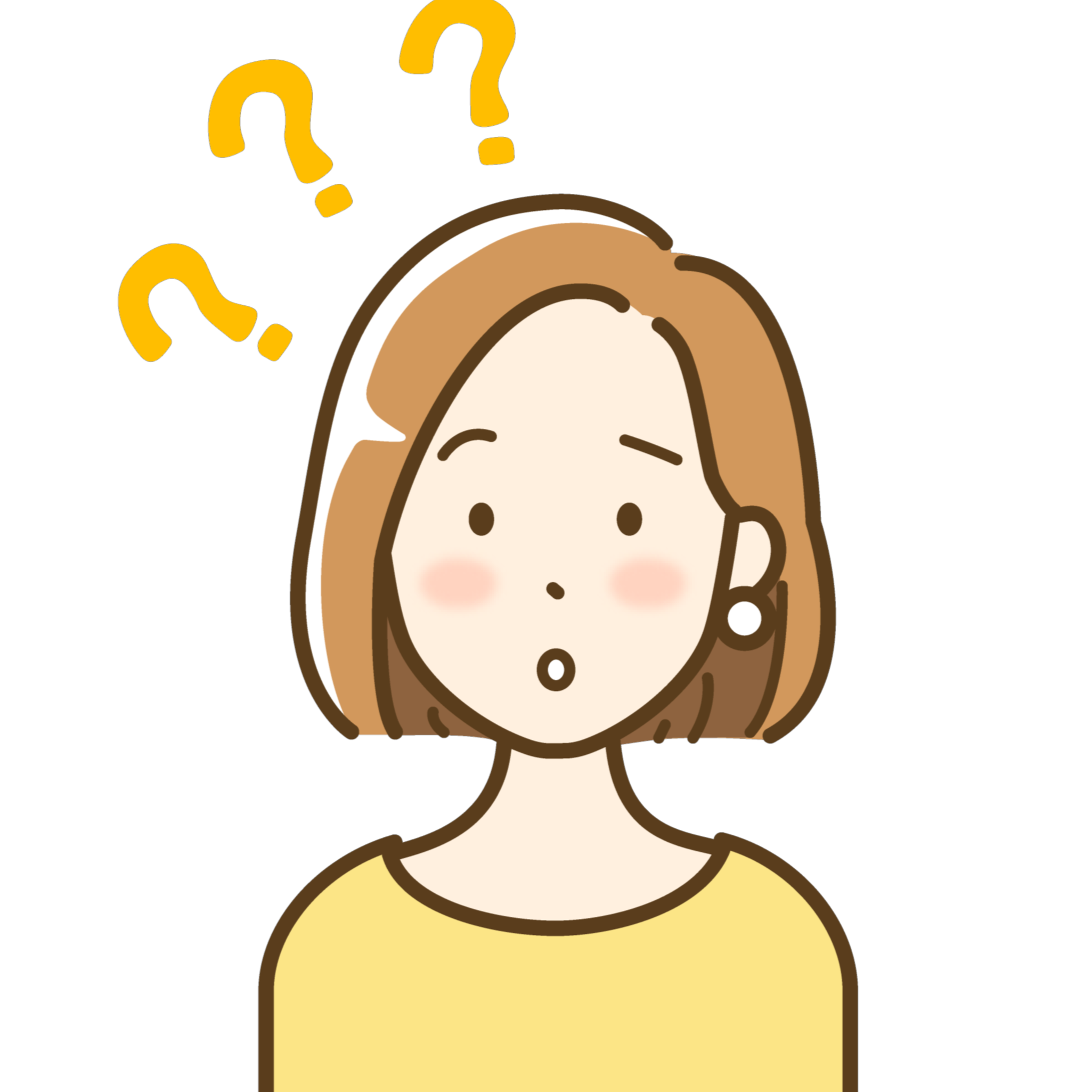
毎日同じ環境にしてあげることで、赤ちゃんも安心できるのかな?



はい! [marker color=”yellow”]小さな変化でも、赤ちゃんには大きな影響[/marker]があるんだそうです。
赤ちゃんは環境の変化に敏感だからこそ、[marker color=”yellow”]毎日同じ条件を整えてあげることで安心できる[/marker]んですね。
環境を整えるって、最初は面倒に感じることもありますが、一度習慣になると逆に楽になりますよ。
赤ちゃんも「あ、寝る時間だ」って分かるみたいです。
【第2段階ステップ】生活リズムを整える(2週間)
環境が整ったら、次は[marker color=”yellow”]生活リズム[/marker]を見直しましょう。
★具体的な方法
- 毎日同じ時間に起こす
- 食事の時間を一定にする
- お昼寝の時間を決める
- 夜の就寝時間を一定にする
最初は思うようにいかなくても、[marker color=”yellow”]続けることが大切[/marker]です。
[marker color=”yellow”]赤ちゃんは習慣を覚えるのに時間がかかる[/marker]ので、気長に取り組みましょう。



今日はうまくいかなかったけど、明日もがんばってみよう!



そう! その前向きな気持ちがとても大切です。
「今日もダメだった…」って落ち込む日もありましたが、1週間、2週間と続けていると、少しずつ変化が見えてきました。
赤ちゃんって、ちゃんと覚えてくれるんですよね。



毎日の積み重ねが大事なのね!
【第3ステップ】赤ちゃんに合わせた対応を考える(3週間目以降)
第1ステップ、第2ステップを試してもうまくいかない場合は、赤ちゃんの[marker color=”yellow”]個性に合わせた対応[/marker]を考えましょう。
★具体的な対応例
- 音に敏感な赤ちゃん:ホワイトノイズを試してみる
- 動きが活発な赤ちゃん:お昼寝前の活動時間を調整する
- 人見知りが強い赤ちゃん:いつもの場所で寝かしつける



私の友人のお子さんは、掃除機の音で寝る不思議な赤ちゃんでした。
最初は「えっ?」と思いましたが、赤ちゃんにはそれぞれ好みがあるんだと勉強になりました。
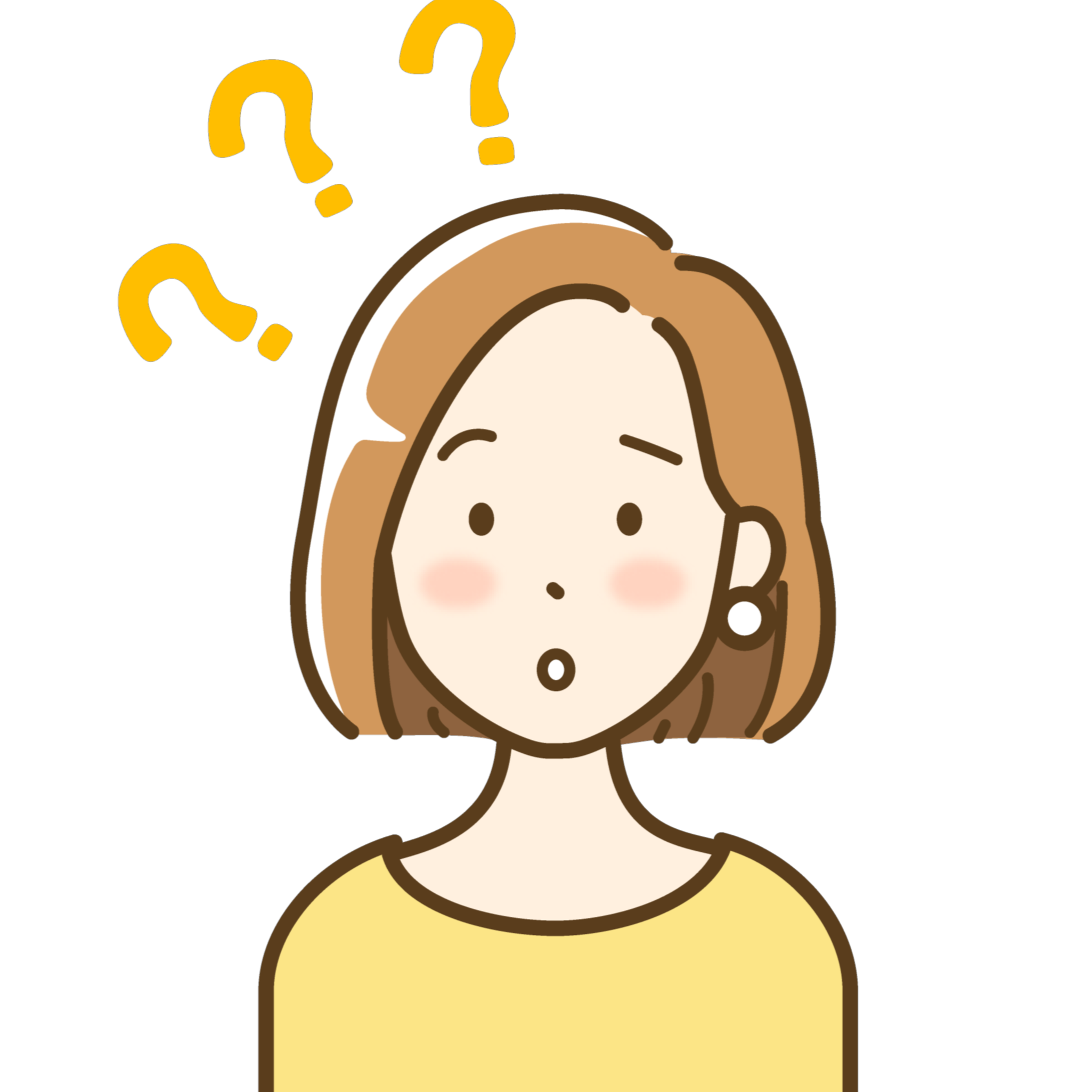
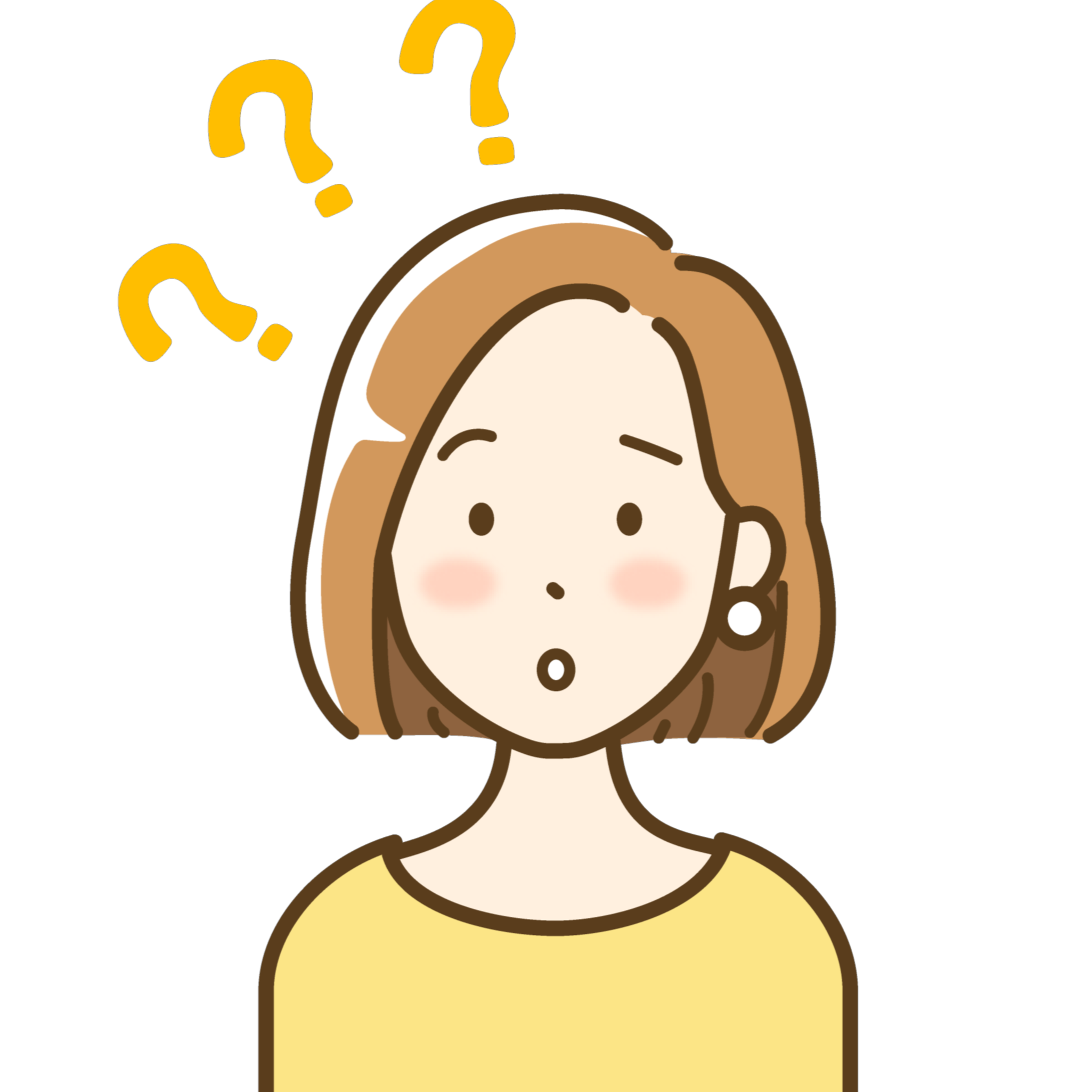
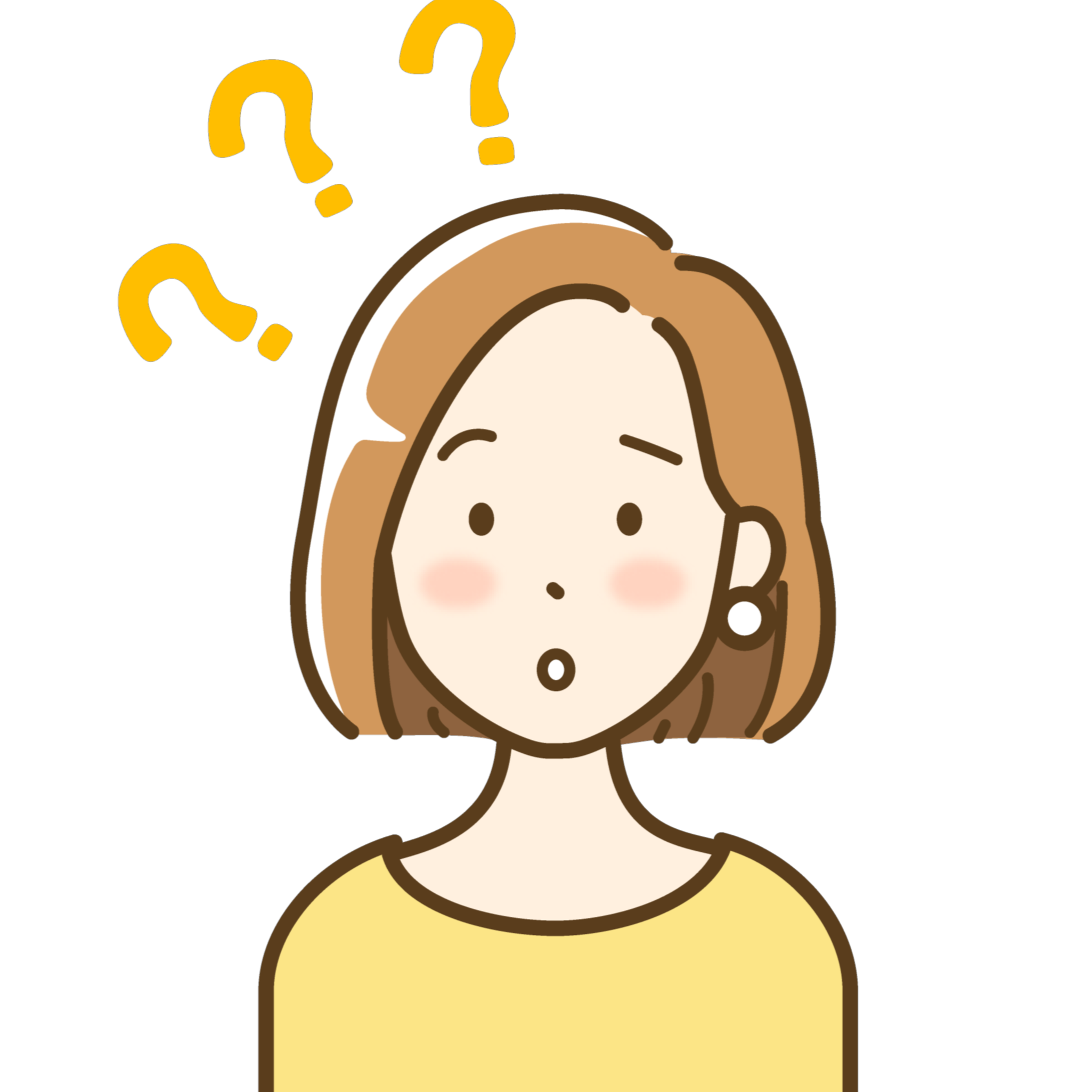
うちの子だけの特別な方法があるかも?



はい! [marker color=”yellow”]赤ちゃんの個性を受け入れること[/marker]で、意外な発見があるかもしれませんよね。
「常識」や「普通」にとらわれすぎないことも大切だなって感じます。
我が子に合う方法が見つかると、育児がぐっと楽になりますよね!



色々と試してみて、うちの子に合った方法を見つけてみたいな!
月齢別のお昼寝パターン参考例


生後6ヶ月前半(6ヶ月0日~15日)
- 午前のお昼寝:10:00~11:00頃(1時間程度)
- 午後のお昼寝:13:00~15:00頃(2時間程度)
- 夕方のお昼寝:16:30~17:30頃(1時間程度)
生後6ヶ月後半(6ヶ月16日~30日)
- 午前のお昼寝:10:00~11:30頃(1時間30分程度)
- 午後のお昼寝:13:30~15:30頃(2時間程度)
このパターンも、あくまで参考です。
[marker color=”yellow”]赤ちゃんの様子を見ながら、調整[/marker]してくださいね。
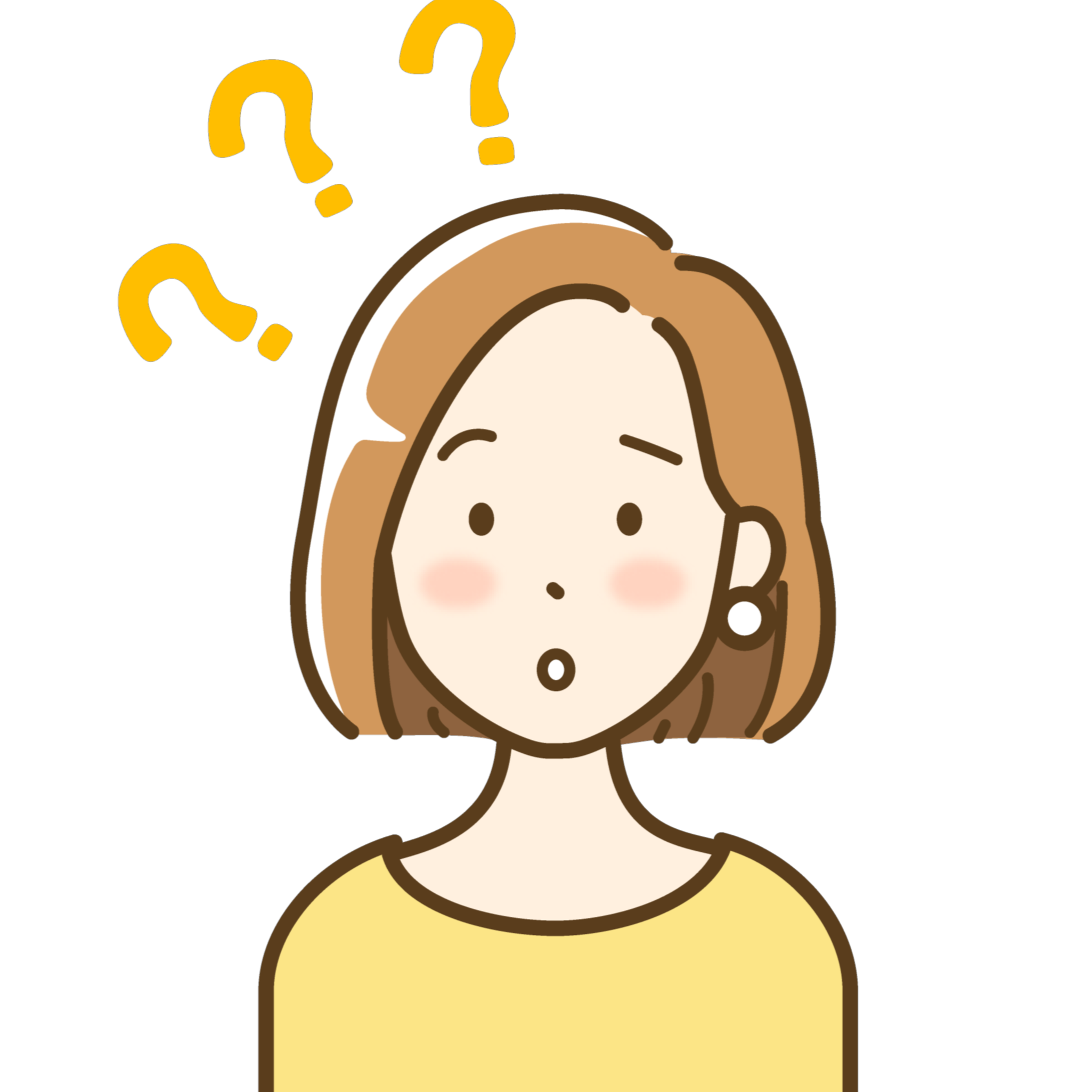
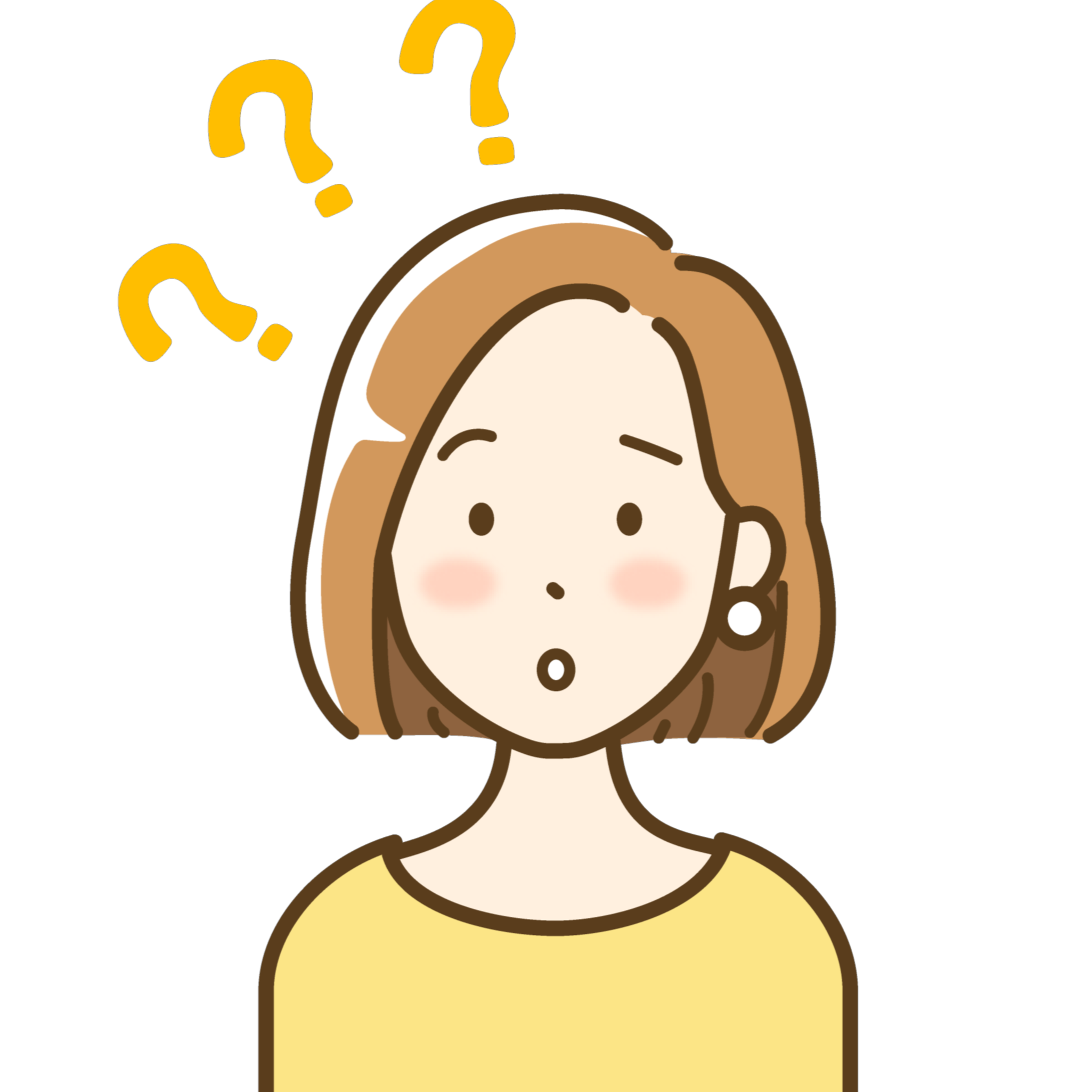
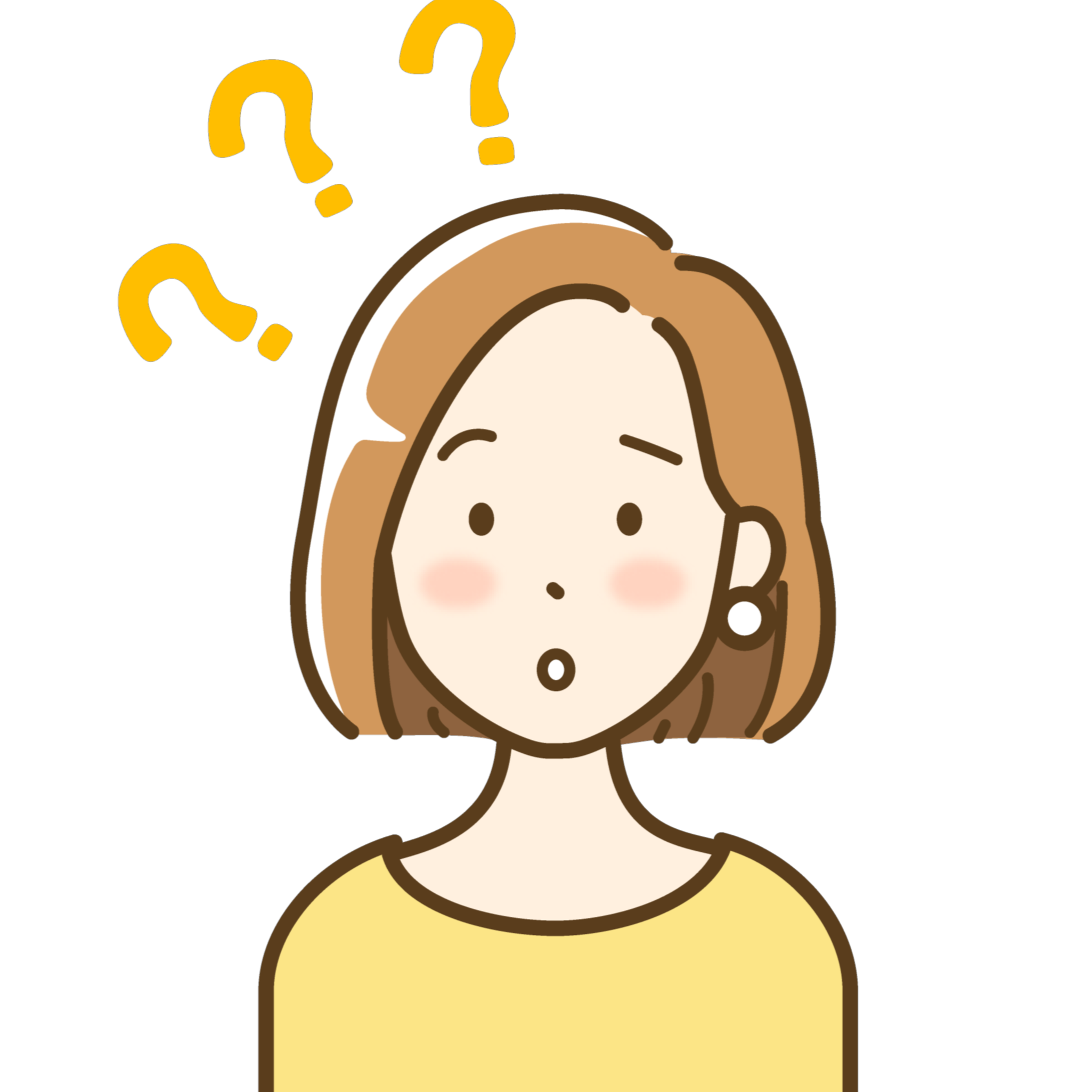
この時間通りにいかなくても、うちの子のペースで大丈夫?



もちろんです! [marker color=”yellow”]時間はあくまで目安[/marker]。
[marker color=”yellow”]赤ちゃんが教えてくれるサインの方が、何倍も大切[/marker]です。
[marker color=”yellow”]時間に縛られすぎず、赤ちゃんの様子を一番に考えて[/marker]あげてくださいね。
ママの心のケア
完璧を求めすぎない
[marker color=”yellow”]お昼寝がうまくいかない日があっても、それは普通のこと[/marker]です。
育児書通りにいかなくても、赤ちゃんは元気に育っています。



完璧じゃなくても、愛情いっぱいに育てられていたら、それでいいよね!



それが一番です!
私も「なんで育児書通りにいかないの?」って悩んでいましたが、先輩ママに「育児書はあくまで参考よ」って言われて、肩の力が抜けました。
「今日はこんな感じだったな」くらいの気持ちで過ごしていきましょうね!
他の赤ちゃんと比較しない
SNSで他の赤ちゃんの様子を見ると、「うちの子だけお昼寝しないのかな・・・」と不安になることがあります。



よその子と比べちゃダメよね。
みんなそれぞれ違っていて、当たり前!



本当にその通りです! 赤ちゃんにはそれぞれ個性があります。
誰かと比べずに、[marker color=”yellow”]我が子のペースを大切に[/marker]しましょう。
SNSの情報はあくまで一部分。
みんなそれぞれ違う悩みを抱えているものです。
疲れた時は休む
赤ちゃんがなかなかお昼寝してくれず、1日中ずっと向き合っていると、本当に疲れてしまいますよね。
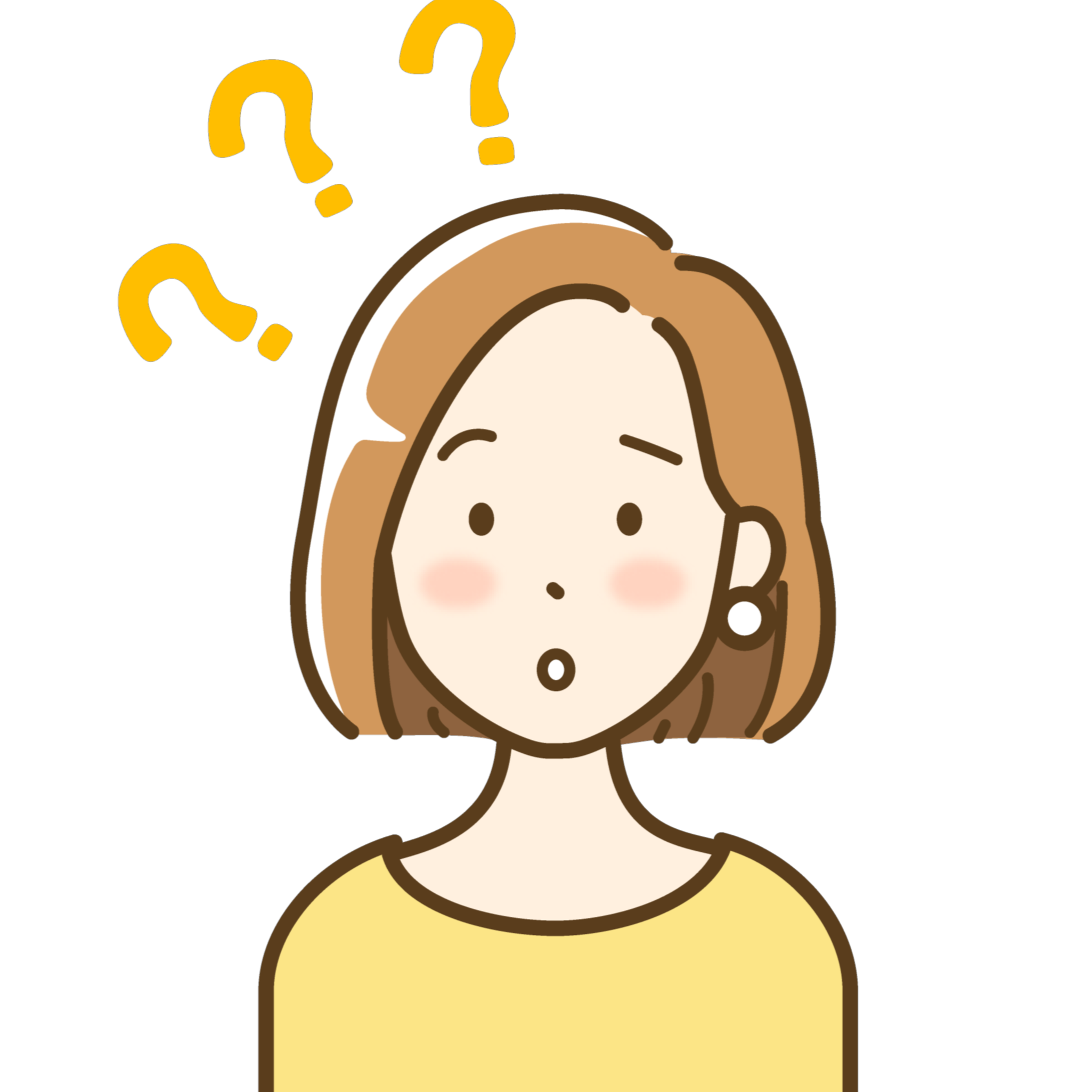
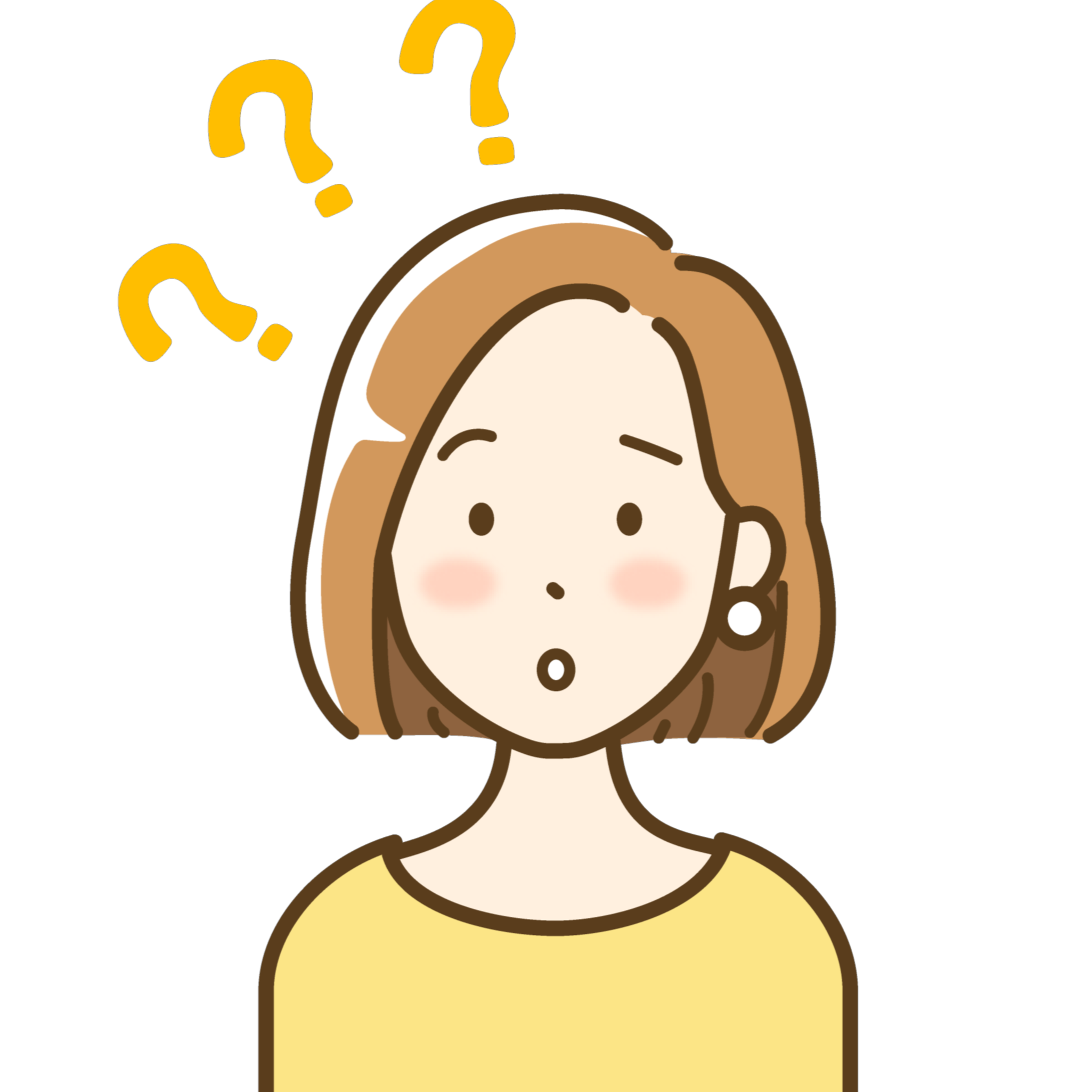
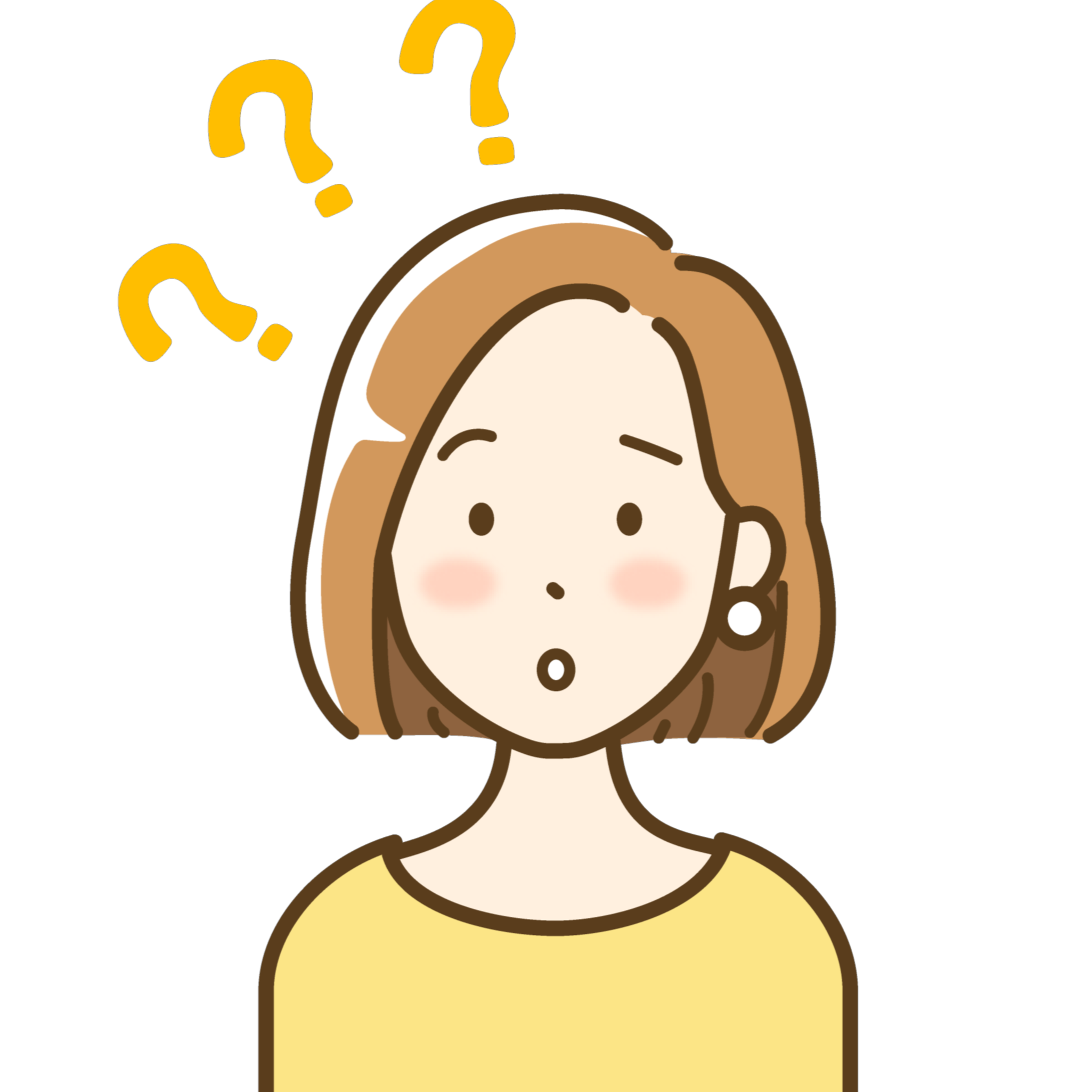
今日は疲れたから、手抜きでもいい?



それで全然大丈夫! [marker color=”yellow”]家事が完璧でなくても、ママが休むことが一番大切[/marker]です。
頼れる人がいる時は、遠慮せずに助けを求めてくださいね。
「私が頑張らなきゃ」って思いがちですが、疲れた時は「今日は手抜きの日」って決めちゃいます。
お惣菜やカップラーメンの日があっても大丈夫!
専門家に相談する目安
もし、赤ちゃんのお昼寝のことで悩んでいて、以下に当てはまるような場合は、[marker color=”yellow”]小児科や保健師さんに相談すること[/marker]をおすすめします。
- 夜もほとんど眠らない
- お昼寝を全くしない状態が1ヶ月以上続く
- 機嫌が悪い状態が続く
- 発達に心配がある
- ママの体調や精神的な負担が大きい
[marker color=”yellow”]一人で悩まず、専門家のアドバイスを受けることで、安心できますし、気持ちも楽に[/marker]なります。



一人で抱え込まないで、相談してみようかな…



はい!どうか、一人で悩まないでくださいね。
専門家の方々は、たくさんのママたちの相談に乗ってきているので、きっと良いアドバイスをくれるはずです。
まとめ
生後6ヶ月の赤ちゃんがお昼寝しないのは、成長過程の自然な変化です。
[marker color=”yellow”]睡眠リズムが大人に近づく大切な時期[/marker]だからこそ、一時的に不安定になることがあります。
大切なのは、[marker color=”yellow”]赤ちゃんの個性を理解し、焦らずに環境や生活リズムを整えること[/marker]です。
すぐには結果が出なくても、継続することで必ず改善されます。
POINT
- 睡眠環境を整える
- 生活リズムを見直す
- 赤ちゃんの眠気のサインを見逃さない
- ママの心のケアも忘れずに
そして何より、[marker color=”yellow”]ママ自身が無理をしないこと[/marker]が一番大切です。
赤ちゃんのお昼寝の悩みは、多くのママが経験することです。
一人で抱え込まず、周りの人に相談したり、同じような経験を持つママたちと情報交換したりしながら、この時期を乗り越えていきましょう。
「うちの子のペースで大丈夫!」そんな気持ちで、今日も一歩ずつ、[marker color=”yellow”]育児を楽しんで[/marker]いきましょうね。



きっと大丈夫。みんなで頑張ろう!



はい! [marker color=”yellow”]一人じゃありません[/marker]。同じような悩みを持つママたちと一緒に、支え合いながら頑張っていきましょう!
この記事が少しでも皆さんのお役に立てれば嬉しいです。
お昼寝の悩みは必ず解決します。
焦らず、赤ちゃんのペースに合わせていきましょう。